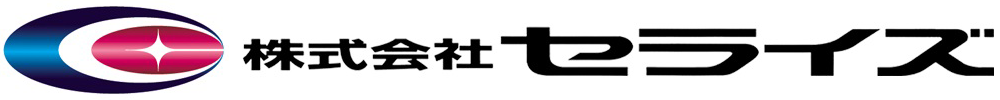誰もが一つぐらい、小林一茶の俳句を覚えていることと思います。
私が一番好きな一茶の俳句は「名月を 取ってくれろと 泣く子かな」というものです。
誰でも知っている小林一茶ですが、その生涯が苦難の連続だったということはあまり知られていないと思います。
まずは、その生涯を書き出してみましょう。
1763年 信濃国(現在の長野県)に生まれる
1765年(3歳)母死去
1770年~1776年 継母が来ていじめられる(異母弟誕生)
1777年(15歳)江戸に奉公に出される。職業を転々とするうち、俳諧と出会う
1801年(39歳)父死去(遺言で遺産分配を明記)
1802年~1813年 遺産分割問題を争う(継母、異母弟と)
1814年(52歳)結婚
1816年(54歳)長男死去
1819年(57歳)長女死去
1821年(59歳)次男死去
1823年(61歳)妻と三男死去
1824年(62歳)再婚すぐに離婚
1826年(64歳)再再婚
1827年(65歳)大火で母屋焼失。その後土蔵で暮らすうち、持病が悪化して死去
1828年(66歳)一茶の死後に次女誕生
※ 年齢は数え年
ここまで、いろいろ苦難がある人はそんなにいないと思います。
私は今回、調べてみて初めて知り、たいへん驚きました。
一茶は生涯に2万以上もの俳句を遺したそうです。
テレビでもおなじみの齋藤孝・明治大学教授が、小林一茶に関する本『心を軽やかにする小林一茶名句百選』(致知出版社)を出版されたと知ってさっそく購入しました。
その中で、印象深かった句を2つご紹介します。
「をり姫に 推参したり 夜這星」
七夕は織姫と彦星が1年に1度会うという伝説。逢瀬を楽しみにしている織姫のところに、彦星ではない流れ星が呼ばれてもいないのに夜這をかけるという、ユニークな句です。
「たのもしや てんつるてんの 初袷」
初めて着た袷(あわせ)の丈がもう短くなったと、子どもの成長の早さを喜んでいる句です。
齋藤先生曰く、
「一茶はどんな大変な状況にあっても自分のことをどこか客観視してその思いを句に昇華させ、ときに自分自身を笑ったり静かに鼓舞しながら強かに生き抜く姿勢を示しています。凄まじいまでの精神力です」
とのこと。
これを機会に、小林一茶の俳句に触れて、齋藤先生の著書のタイトルどおり「心を軽やかに」していきたいと思います。